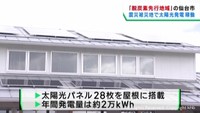女川原発で重大事故が起きたことを想定した宮城県などによる訓練が、8日に女川町などで行われました。2号機が再稼働して以来、住民が参加した初めての訓練でしたが参加者からは不安の声も聞かれました。
訓練は、地震による津波で被害を受けた女川原発2号機から放射性物質が放出されたという想定で、原発周辺の住民約210人と自治体関係者らが参加しました。
今回の訓練では初めて、牡鹿半島の孤立した集落に自衛隊がヘリコプターを使って物資を届けました。
集落にある福祉施設では、防護服を着た職員が支援物資などに付いた放射性物質を測定した上で受け取っていました。
栗原市では、女川町からバスや自家用車で避難してきた30人余りの住民がスマートフォンのアプリなどを使い手続きをしました。 女川原発で重大事故が起きた場合、女川町では約5800人の全ての住民が避難しなければなりません。
12月に本土側と結ぶ橋が開通した出島から車で避難してきたという男性は、橋ができ避難しやすくなったと話す一方で課題も感じたと言います。
「実際、島民で車を持っている方と持っていない方、足が不自由で歩くのが大変な方もいる。どのように避難しないといけないかは島民の中で話をしないといけないと思っている」
原発の近くから車とバスで避難してきた男性は、地震で道路が寸断され孤立することが気掛かりと話します
「東日本大震災の時は孤立しましたからね。下の道路はどっちへも行かれない状態になった。(実際の避難は)なかなか難しいと思います」
宮城県原子力安全対策課長谷部洋課長「防災計画に完璧や終わりは無いと認識していますので、常により効果的なことを検証していきたい」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ